介護施設必見!ミャンマー人受け入れの3つのメリットとは?現場の声と成功事例を紹介
人手不足に悩む介護施設へ。なぜ今ミャンマー人材なのか?文化・制度・実例から、信頼できる受け入れの全ステップを解説します。
【はじめに】ミャンマー人材受け入れを考える介護施設の皆さまへ
「人が足りない」──これは、ただの現実ではなく、介護現場の叫びです。
高齢化が進み、介護のニーズは高まる一方。けれど、担い手は減っていく。
特に、地方の中小施設では「募集しても応募がない」「やっと採用できてもすぐに辞めてしまう」──そんな声が、日常のように聞こえてきます。
そこでいま、静かに注目を集めているのが──ミャンマー人材の受け入れです。
外国人材、それも“ミャンマー人”が選ばれる理由
単に「労働力を埋めるため」──そう思っているとしたら、それは誤解です。
ミャンマーには、年長者を敬い、人に優しく接する文化が根付いています。
その心は、介護の現場でも自然とあらわれる。
千葉県のある施設では、「ありがとう」と感謝の声をかけられる場面が増え、その誠実な姿勢に、利用者の笑顔が戻ってきました。
文化が、ケアに生きる。それが、ミャンマー人材の大きな魅力なのです。
「受け入れても、すぐ辞めてしまうのでは?」「文化の違いで、現場が混乱しないか?」
そんな不安にも、データと実例で応えていきます。
そして読み終えるころ、きっとこう感じていただけるはずです──
「ミャンマー人材は、心に寄り添えるパートナーだ」と。

■ミャンマー人材を受け入れる、3つの理由なぜ、ミャンマー人なのか?その答えを、3つの視点から紐解きます。
▼1. 思いやりの文化が生む「寄り添う力」
仏教の教えが日常に息づく国、ミャンマー。そこでは、年長者や弱い立場の人を敬う心が育まれています。
ある関西の施設では、利用者の話にじっくり耳を傾け、ときに涙を流しながら寄り添う姿が見られました。
「まるで家族のようだ」──そんな声が、利用者の口から自然にこぼれるのです。
▼2. 日本語を学ぶ意欲と、長く働きたいという想い
介護は、言葉の仕事でもあります。
ミャンマー人材は、来日前から日本語を真剣に学び、特定技能の試験に合格して来日します。
驚くべきはその“覚悟”。
ある調査では、約8割のミャンマー人希望者が「5年以上働きたい」と回答しています。
一時的な出稼ぎではない。人生をかけて、介護に向き合おうとする人たちなのです。
▼3. 制度と仕組みが整っている、だから“安心”できる
外国人材の受け入れには、制度面の不安もあるでしょう。
でも、ミャンマーは日本政府と正式な協定を結んでおり、技能実習・特定技能ともに、スムーズな手続きが可能です。
また、登録支援機関を通じて行えば、事前研修・住居・日本語教育・生活支援までワンストップで整います。
送り出しも、政府認定の機関のみ。だからこそ、信頼性が高く、トラブルも少ないのです。
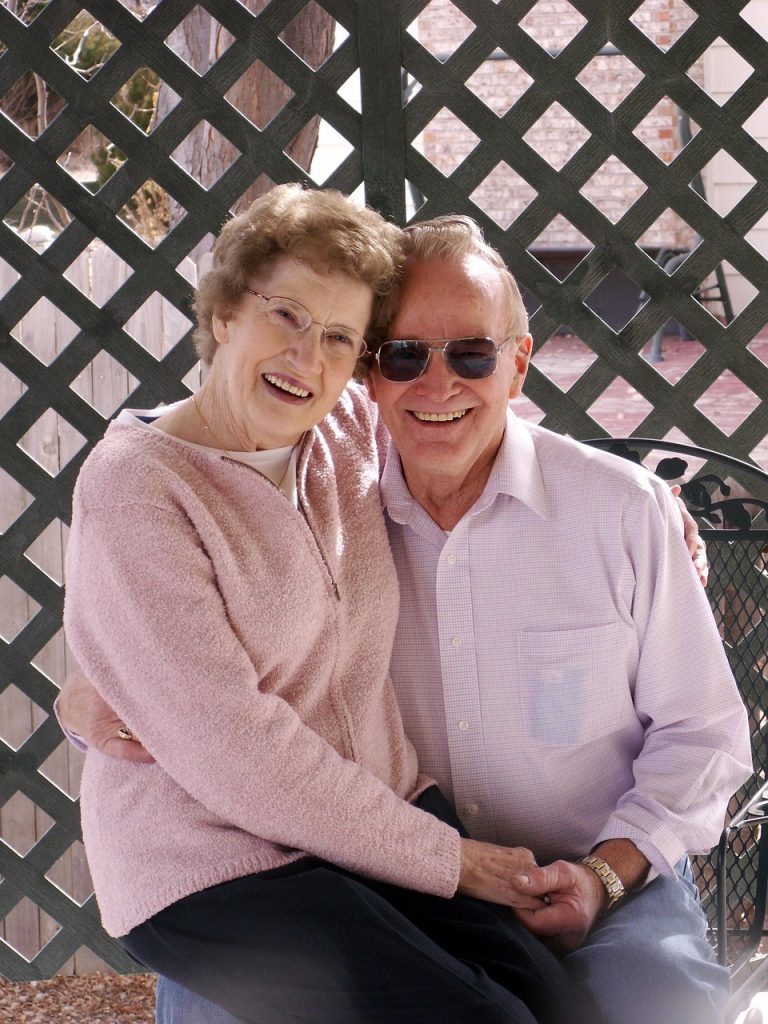
■現場からの声──“共に働いて、気づいたこと”
理屈や制度の話だけでは、まだ不安かもしれません。だからこそ、現場の声を届けたいのです。
福井の特別養護老人ホーム。3年前、ミャンマー人2名を初めて採用。
現在、その2名は変わらず勤務を続け、定着率は100%。
文化交流の場を設け、挨拶を練習し、母国料理の日を開催した──その“小さな積み重ね”が、定着の大きな要因でした。
熊本のデイサービスでは、認知症の利用者が手を握り、「ありがとう、あんたに助けてもらってるんだよ」とつぶやいた。
言葉以上に、心が通じ合った瞬間。
東京の中規模施設では、穏やかなミャンマー人の接し方が、職場全体の空気をやわらかく変えました。
──そう。ミャンマー人材は、“現場を変える力”を持っているのです。
■採用前に知っておきたい受け入れ時のポイントと注意点
「採用すれば、それで終わりではない」
むしろ、本当の始まりはそこからです。
どれほど優れた人材であっても、環境が整っていなければ、その力を発揮することはできません。
ミャンマー人材の受け入れには、やさしさと同じくらいの準備と理解が必要なのです。
▼言葉の壁──それは“心の壁”にもなりうる
日本語ができる。それだけで安心してはいけません。
現場で使われる専門語、微妙なニュアンス、行間の空気。
それらは教科書では学べません。
ある施設では、入職後2週間、先輩スタッフがそばに寄り添い、言葉と仕事の両方をサポートしました。
結果、不安は薄れ、笑顔が増えていったのです。
▼文化を知らずに人を迎えることは、地図を持たずに旅を始めるようなもの
ミャンマーでは、目上に強く言い返すことを避けます。
それが「意見を言わない」と誤解されることも。
だからこそ、文化を知ること。
違いを恐れず、理解しようとすること。
それが、信頼のはじまりです。
ある施設では、初日に「ミャンマー文化紹介の時間」を設けました。
小さな工夫が、大きな安心につながったのです。
▼制度の複雑さは、信頼できる“伴走者”で乗り越えられる
在留資格の手続き。
生活支援、日本語教育、住まいの準備。
一つひとつは大変かもしれません。
でも、登録支援機関という専門家と組めば、その道はずっと歩きやすくなります。
実際、初めての外国人採用でもスムーズに進んだ例がたくさんあります。

■制度理解と準備の進め方:ミャンマー人材の受け入れステップ
「知らなかった」が、トラブルの一番の原因です。
技能実習と特定技能──
どちらも外国人材の受け入れ制度ですが、目的も条件も異なります。
技能実習は、技能移転。
特定技能は、人手不足の解消。
あなたの施設には、どちらが合っているのか。
それを見極めるところから、すべてが始まります。
また、送り出し機関も重要です。
誰から紹介されるのか?
そこに信頼はあるのか?
ヤンゴンのある機関では、150時間以上の日本語研修を行い、
人柄や志望動機も丁寧に確認したうえで人材を送り出しています。
「誰でもよい」ではなく、「あなたの施設に合う人」を。
そして、最後にもう一つ。
気になる「コスト」についても、忘れてはいけません。
たしかに、準備には費用がかかります。
ですが、補助金や支援制度の活用で、それはぐっと現実的になります。
【まとめ】ミャンマー人は日本の介護現場の「ベストパートナー」
介護とは、技術の前に「心」でありたい。
その「心」を、静かに、けれど確かに届けてくれるのが、ミャンマーの人たちです。
思いやりの文化。
敬う気持ち。
感謝を大切にする姿勢。
すでに多くの施設で、ミャンマー人材が利用者の心に寄り添い、
頼られ、感謝される存在になっています。
それは、「文化を超えて、心がつながった」証です。

次の一歩は、“対話”から始まる
「まずは、話を聞いてみませんか?」
信頼できる支援機関に相談する。
施設を訪問して、実際の様子を見てみる。
その一歩が、きっとあなたの施設に、新しい風を吹き込んでくれるはずです。
可能性は、出会いの中にあります。
そして、出会いは──“行動”から生まれるのです。
LINEのお友達登録で、以下の2つの特典をプレゼントします。
● 「外国人材受入制度の基礎と最新動向」セミナー動画&PDF資料
特定技能制度などを活用した新しい働き方を徹底解説。外国人雇用の全体像から成功の秘訣まで、この1本でまるごと理解できます。
● Google Meetによる無料個別相談(60分)
あなたの会社・施設に最適な外国人採用について、専門家が1対1でアドバイス。面談後には、貴社専用の「外国人雇用の処方箋」を無料で作成・進呈します。
※本記事は2025年4月時点の情報に基づいて執筆されています。今後、法改正・制度運用変更等が行われる場合がありますので、最新情報は出入国在留管理庁やJITCOの公式発表をご確認ください。※掲載されている事例の一部は、取材結果を元に再構成しています。個人や企業が特定されないよう一部内容を変更しています。※記事内に記載された制度情報・運用情報は、法人向け人材採用の判断材料としてご活用ください。個別ケースへの適用にあたっては、専門家や支援機関への相談を推奨します。




