ミャンマー人介護人材受け入れにかかる総費用まとめ
ミャンマー人介護人材受け入れにかかる費用は?
介護施設の採用担当者として一番気になるのは、「結局、うちで受け入れたらいくらかかるのか?」という点ではないでしょうか。この記事では、ミャンマー人介護人材を受け入れる場合の総費用を、支援制度を活用したケースも含めてわかりやすくまとめます。まずは、おおまかな金額感をつかんで、受け入れに向けた第一歩を踏み出しましょう。
初年度に必要な総額はいくら?【実例付き】
結論からお伝えします。
ミャンマー人介護人材を受け入れる場合、初年度にかかる総額は「約120万〜180万円」が目安です。
この金額には、以下のような費用が含まれます。
- 人材紹介料(20万〜60万円)
- 渡航費用(10万〜15万円)
- 在留資格申請サポート費(5万〜10万円)
- 登録支援機関への委託費(月2万〜3万円 × 12か月=24万〜36万円)
- その他:生活準備金(家具家電の購入、初期費用などで20万〜30万円)
施設の規模や地域、紹介会社によって若干差はありますが、おおよそこの範囲に収まることが多いです。
たとえば、ある地方都市の中規模施設では、
紹介料40万円、渡航費用12万円、初期生活準備費25万円、支援委託費30万円、ビザ申請5万円で、合計約112万円だったケースもあります。
費用の内訳とタイミング|採用前後でかかるコスト
費用は、採用プロセスのどの段階で発生するかを把握しておくことが大切です。
大まかな流れは以下のとおりです。
- 【採用決定時】人材紹介料の支払い(契約時または内定後すぐ)
- 【渡航前】渡航費用・ビザ申請費用の支払い
- 【渡航後すぐ】住居準備費用(敷金・礼金・家具家電購入など)
- 【毎月】登録支援機関への支援委託費(月2〜3万円程度)
特に注意したいのは、採用決定から渡航までに一括でかかる初期費用です。
資金計画をしっかり立てておかないと、思わぬタイミングで大きな出費が発生する可能性があります。
また、登録支援機関への支払いは毎月発生するため、年間支出にもきちんと組み込んでおきましょう。
支援制度・助成金を活用した場合の実質負担額
支援制度を活用すれば、実質負担額を大きく抑えることが可能です。
たとえば、
- 地方自治体の「外国人介護人材受け入れ支援事業」補助金(上限50万円)
- 介護分野に特化した「国や自治体が提供する各種支援金・助成制度」
これらを活用できた場合、
初年度総額150万円が、実質100万円以下にまで抑えられるケースもあります。
特に中小規模の介護施設にとっては、助成金の活用が受け入れ成功のカギです。
支援対象となる条件(例:人数制限、申請タイミング)を事前に確認し、漏れなく申請することが重要です。
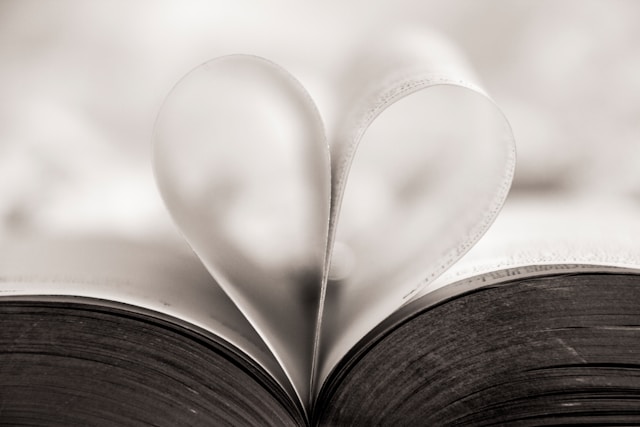
ミャンマー人介護人材の特徴|なぜ日本の介護現場に向いているのか?
「外国人介護人材を受け入れるなら、どの国の人がいいのだろう?」と考えたことはありませんか。ここでは、ミャンマー人介護人材の特徴について詳しく解説します。文化や性格、日本の介護現場にどのようにフィットするのか、他国人材との違いも比較しながら見ていきましょう。
ミャンマー人材の基本情報(年齢層・文化・就労意欲)
まず、ミャンマー人介護人材の基本的な特徴を押さえておきましょう。
ミャンマーは若い人口が多く、20代前半〜30代前半の労働力が豊富です。
これは、高齢化が進む日本にとって非常に心強いポイントです。
文化面では、ミャンマー人の多くが仏教徒です。
「目上の人を敬う」「人に尽くす」という価値観が根付いており、介護の現場でもこの文化的背景が活きます。
さらに、経済事情もあり、海外で働きたいという就労意欲は非常に高いです。
特に日本は「安全」「収入が安定している」「技術が学べる」と人気があり、志望動機がしっかりしている人が多いのも特徴です。
他国人材(フィリピン・ベトナム)との比較|メリットと注意点
ミャンマー人とフィリピン人、ベトナム人を比較してみましょう。
【フィリピン人】
- 明るく社交的だが、自己主張が強めな傾向
- 英語力が高い一方、日本語習得にやや時間がかかることも
【ベトナム人】
- 真面目で努力家だが、プライドが高く、人間関係のトラブルに注意が必要
【ミャンマー人】
- 穏やかで控えめ、指示に素直に従う傾向が強い
- 日本語学習に真剣で、コツコツ型
- ただし、異国の文化や環境に強い緊張を感じる人も多いので、受け入れ初期のサポートが重要
このように、ミャンマー人は日本人の感覚に比較的近く、介護職との相性が良いといわれています。
※ 本記事で紹介している各国の「性格傾向」や「国民性」については、現場で多く聞かれる一般的な印象・傾向をもとにしています。当然ながら、個々の人材には多様な背景や個性があり、一概に国籍だけで性格や適性を判断することはできません。採用にあたっては、国籍だけでなく、人柄や価値観、コミュニケーションの姿勢といった“個人としての特性”を丁寧に見極める視点が重要です。
定着率が高い理由と現場での評判
ミャンマー人介護人材は、他国人材と比べても定着率が高い傾向にあります。
その理由は大きく3つあります。
- 家族思いな文化
ミャンマーでは家族を大切にする文化が強く、介護という「家族をケアする仕事」に誇りを持ちやすいです。 - 目上を敬う教育
年上を敬い、言葉遣いや態度にも気をつけるため、日本の介護施設で好感を持たれやすいです。 - 長期的な視点でのキャリア志向
「数年で辞める」のではなく、「日本でスキルを身につけて将来に活かしたい」という考えを持っている人が多いです。
実際に、ある中小規模施設では、ミャンマー人を採用してから離職率が大きく下がったという報告もあります。
「とても丁寧に仕事をしてくれる」「笑顔が多く、利用者さんにも好評」などの声が多く寄せられています。

ミャンマー人介護人材受け入れ|使える支援制度・助成金まとめ
ミャンマー人介護人材の受け入れには、費用がかかるとわかっていても、「本当にうちで負担できるのか?」と不安になる方も多いでしょう。安心してください。国や自治体には、外国人介護人材の受け入れを支援する制度や助成金が用意されています。この章では、使える支援制度をわかりやすく紹介し、費用負担を軽くする方法をお伝えします。
国の支援制度(特定技能支援・登録支援機関サポート)
まず、国が提供している支援策について説明します。
外国人介護人材を受け入れる場合、多くの施設は「特定技能」ビザを利用します。
この特定技能制度では、受け入れ企業に対して義務付けられている支援(生活サポート、相談対応、日本語学習支援など)を、登録支援機関に委託することができます。
登録支援機関に委託することで、
- 定着支援の専門家によるサポートが受けられる
- 書類作成や手続きの負担が大きく軽減される
といったメリットがあります。
もちろん、登録支援機関への支援委託費(月2~3万円程度)は必要ですが、
自力で支援体制を構築するコストと労力を考えれば、結果的に安く・安全に運用できるケースがほとんどです。
地方自治体の補助金活用術|費用負担を減らすコツ
さらに注目すべきは、地方自治体が提供している独自の助成金や補助金です。
たとえば、ある県では、
- 「外国人介護人材受け入れ支援補助金」として、受け入れ1人あたり最大50万円支給
- 「住居整備助成金」として、家電購入費や賃貸契約初期費用の一部補助
など、かなり手厚いサポートが行われています。
ただし、こうした助成金は
- 予算枠が限られている(先着順の場合も)
- 申請書類が複雑な場合がある
ため、早めの情報収集と申請準備がカギとなります。
受け入れを検討する段階で、必ず自治体のホームページや窓口に問い合わせ、最新情報をチェックしましょう。
支援制度を使うために押さえるべき注意点
支援制度は便利ですが、利用にあたって注意すべき点もあります。
- 対象要件を満たす必要がある
たとえば、「支援制度の対象は中小企業のみ」といった制限がある場合もあります。事前に要件確認が必須です。 - 期限内に申請すること
支援金や助成金には、申請受付期間が決められていることが多いです。タイミングを逃すと、せっかくのチャンスを失うリスクがあります。 - 適切な報告・管理が求められる
受給後は、定期的な報告書提出や使用用途の証明を求められる場合もあります。しっかり管理できる体制を作っておくことが大切です。
これらを踏まえ、受け入れ準備段階から支援制度活用を前提にスケジュールを組むと、スムーズに進められます。

ミャンマー人介護人材受け入れ|手続きと流れを5ステップで解説
「ミャンマー人介護人材を受け入れるのは大変そう」と感じる方もいるかもしれません。でも実際は、流れをきちんと押さえれば、それほど難しいものではありません。この章では、受け入れまでの手続きを、5つのステップに分けてわかりやすく解説します。イメージをつかめば、行動に移すハードルがぐっと下がりますよ。
【STEP1】紹介会社・送り出し機関の選び方
最初のステップは、「信頼できる紹介会社や送り出し機関を選ぶこと」です。
ここがズレると、後のトラブル(日本語力不足、ビザ取得ミス、労務問題)につながるため、慎重に選定しましょう。
選び方のポイントは次の通りです。
- ミャンマー政府認定の正式な送り出し機関と提携しているか
- 日本語教育や介護基礎研修を現地で行っているか
- これまでの送出実績(人数・トラブル件数)を開示しているか
- 受け入れ後も相談に乗ってくれるか
面談時には、過去の受け入れ実績データや、候補者の日本語試験結果(例:JLPT、JFT-Basic)を必ず確認しましょう。
【STEP2】採用面接・内定手続き
次に行うのは、採用面接と内定の手続きです。
通常、現地(ミャンマー)でのオンライン面接が主流ですが、紹介会社によっては事前に選抜された「推薦候補者リスト」から選考する方式もあります。
面接時のチェックポイントは、
- 日本語レベル(簡単な自己紹介・意思疎通ができるか)
- 表情や態度(素直さ、学ぶ意欲があるか)
- 介護職への理解度(なぜ介護職を選んだのか)
内定後は、
- 雇用条件通知書(給与、勤務時間、業務内容)
- 雇用契約書
を発行し、本人との間で明確な合意を取り付けます。
ここで曖昧な説明をすると、後々トラブルの原因になりますので、できるだけ丁寧かつ具体的に伝えることが大切です。
【STEP3】在留資格(特定技能)申請の流れ
内定後、在留資格(特定技能1号)の申請手続きに進みます。
申請の流れは以下のとおりです。
- 必要書類の準備(在留資格認定証明書交付申請書、受入機関関係書類、支援計画書など)
- 入国管理局に申請
- 許可が下りるまで約1〜2か月
- 許可後、ミャンマー側でビザ取得 → 渡航準備へ
この手続きは専門知識が必要なため、登録支援機関や行政書士に依頼するのが一般的です。
費用はかかりますが、手戻りや不許可リスクを避けるためにも、プロに任せるのが安心です。
【STEP4】入国・定着支援のスタート
在留資格が許可され、ビザが発給されたら、いよいよ入国となります。
入国後すぐに、以下の支援をスタートします。
- 住居の確保・契約手続き
- 生活オリエンテーション(ゴミ出しルール、公共交通機関の使い方など)
- 日本語学習サポート(定期的なレッスン・会話練習)
特定技能制度では、受け入れ企業または登録支援機関が、こうした支援をきちんと行う義務があります。
最初の1〜3か月が、定着できるかどうかの勝負どころです。
【STEP5】フォローアップで定着率アップ
受け入れて終わりではありません。
長く安心して働いてもらうためには、定期的なフォローアップが欠かせません。
- 1か月・3か月・6か月ごとに面談を設定し、悩みや困りごとを把握する
- 職場の指導担当者を決めて、日々のフォローを行う
- 必要に応じて、日本語教育やスキルアップ支援も継続する
「気軽に相談できる」「自分の成長を感じられる」
そんな環境を整えることが、離職を防ぎ、施設全体の活性化にもつながります。

失敗を防ぐために知っておくべきこと|リスクと成功の分かれ道
ミャンマー人介護人材の受け入れは、多くのメリットがありますが、何も準備しなければトラブルが起きるリスクもあります。この章では、ありがちな失敗例とその原因を紹介し、それを乗り越えて成功するための具体策をお伝えします。「受け入れてよかった!」と思える未来に向けて、ぜひ参考にしてください。
失敗例から学ぶ|日本語力・文化摩擦・支援不足への備え
まずは、実際に起きた失敗例を見てみましょう。
【失敗例1:日本語力不足による業務ミス】
採用時の面接では元気に受け答えできたものの、介護現場の専門用語(例:「陰洗」「体位交換」)が理解できず、業務に支障が出た。
→対策:事前に介護用語リストを用意し、入職前に必ず簡単な実地研修を行うことが重要です。
【失敗例2:文化摩擦によるチーム不和】
日本の「空気を読む」文化に戸惑い、本人は悪気なく行動していたのに、同僚から「協調性がない」と誤解され、孤立してしまった。
→対策:受け入れ側(日本人スタッフ)への異文化理解研修を実施しましょう。本人だけに適応を求めるのではなく、相互理解を深めることが大切です。
【失敗例3:支援不足による早期離職】
仕事以外の生活支援が手薄で、孤独感やストレスから半年以内に帰国してしまった。
→対策:生活支援(住居、交友関係、日本語レッスン)も手厚くサポートする体制を整えることがポイントです。
成功事例紹介|小規模施設でも受け入れに成功したケース
一方、しっかり準備と支援をしたことで、成功している施設もたくさんあります。
【成功例:地方都市の小規模デイサービス】
利用者30名規模のデイサービス施設が、ミャンマー人介護人材2名を受け入れ。
ポイントは次の3つでした。
- 採用前に現地で日本式介護研修を実施
- 日本人スタッフ全員に異文化理解研修を行い、迎える体制を整備
- 入職後も、月1回の日本語教室と個別フォロー面談を実施
結果、ミャンマー人スタッフは利用者から「とても丁寧で優しい」と高評価を受け、2年以上定着。
施設全体の雰囲気も明るくなり、新しい利用者の増加にもつながったそうです。
※掲載されている事例の一部は、取材結果を元に再構成しています。個人や企業が特定されないよう一部内容を変更しています。※記事内に記載された制度情報・運用情報は、法人向け人材採用の判断材料としてご活用ください。個別ケースへの適用にあたっては、専門家や支援機関への相談を推奨します
成功の3つの秘訣|教育・支援・コミュニケーション
ミャンマー人介護人材を受け入れて成功するためには、次の3つが不可欠です。
- 教育を惜しまないこと
- 入職前・入職後も、日本語教育や介護技術指導を継続的に行う。
- 生活支援を手厚くすること
- 仕事だけでなく、生活面でも孤立させない体制を作る。自治体支援も積極的に利用する。
- コミュニケーションを日常に組み込むこと
- 月1回以上の個別面談を必ず行い、悩みを早期にキャッチする。
- 「困ったら相談していいんだよ」という安心感を持たせる。
これらを実践すれば、ミャンマー人材は日本人スタッフと同様に、職場にしっかりと根付き、戦力となってくれるでしょう。

【まとめ】外国人介護人材は意外と現実的な選択肢|まずは相談から始めよう
ここまで読んでくださったあなたは、ミャンマー人介護人材の受け入れにかかる費用や支援制度、成功するためのポイントまで、具体的にイメージできるようになったはずです。最後に、この記事のポイントをまとめながら、次の一歩をどう踏み出せばいいかをお伝えします。
「費用も手続きも意外とクリアできる」ことに気づけたはず
受け入れにかかる総費用は、初年度120万〜180万円ほど。
一見すると大きな負担に見えますが、国や自治体の支援制度を活用すれば、実質負担はぐっと軽くなります。
さらに、ミャンマー人材の高い就労意欲と日本文化への親和性を考えれば、コスト以上の価値がある投資であることがわかります。
手続きも、「5ステップ」でシンプルに整理すれば、それほど難しいものではありません。
信頼できるパートナー(紹介会社・登録支援機関)を選び、必要な支援を整えれば、スムーズに進められるでしょう。
「うちの施設でも受け入れできるかも」と前向きに思えたら
この記事を通して、
「外国人介護人材の受け入れ=ハードルが高い」
という思い込みが、
「うちでもできそうだ」という前向きな気持ちに変わったのではないでしょうか。
もちろん、全く不安がないわけではありません。
けれど、
- 必要な費用が明確になった
- 支援策を使えば負担が軽くなることがわかった
- 成功するための具体的なステップを知った
この3つを手にした今、あなたはもう、スタート地点に立っています。
最初の一歩は「相談してみる」だけでもいい
いきなり受け入れを決断する必要はありません。
まずは、
- 紹介会社に資料を取り寄せる
- 登録支援機関に相談してみる
- 自治体の助成金情報を調べる
そんな「小さなアクション」から始めてみましょう。
行動することでしか、不安は解消できません。
そして、行動した先には、
新しい仲間と、利用者さんたちの笑顔にあふれた介護現場が待っているはずです。
さあ、最初の一歩を踏み出しましょう。
未来は、動き出すあなたを待っています。
LINEのお友達登録で、以下の2つの特典をプレゼントします。
● 「外国人材受入制度の基礎と最新動向」セミナー動画&PDF資料
特定技能制度などを活用した新しい働き方を徹底解説。外国人雇用の全体像から成功の秘訣まで、この1本でまるごと理解できます。
● Google Meetによる無料個別相談(60分)
あなたの会社・施設に最適な外国人採用について、専門家が1対1でアドバイス。面談後には、貴社専用の「外国人雇用の処方箋」を無料で作成・進呈します。
※本記事は2025年4月時点の情報に基づいて執筆されています。今後、法改正・制度運用変更等が行われる場合がありますので、最新情報は出入国在留管理庁やJITCOの公式発表をご確認ください。※掲載されている事例の一部は、取材結果を元に再構成しています。個人や企業が特定されないよう一部内容を変更しています。※記事内に記載された制度情報・運用情報は、法人向け人材採用の判断材料としてご活用ください。個別ケースへの適用にあたっては、専門家や支援機関への相談を推奨します
※ 本記事で紹介している各国の「性格傾向」や「国民性」については、現場で多く聞かれる一般的な印象・傾向をもとにしています。当然ながら、個々の人材には多様な背景や個性があり、一概に国籍だけで性格や適性を判断することはできません。採用にあたっては、国籍だけでなく、人柄や価値観、コミュニケーションの姿勢といった“個人としての特性”を丁寧に見極める視点が重要です。




